Column コラム
2025.04.18
医師の残業時間はどのくらい?長時間労働の現状と解決策について解説
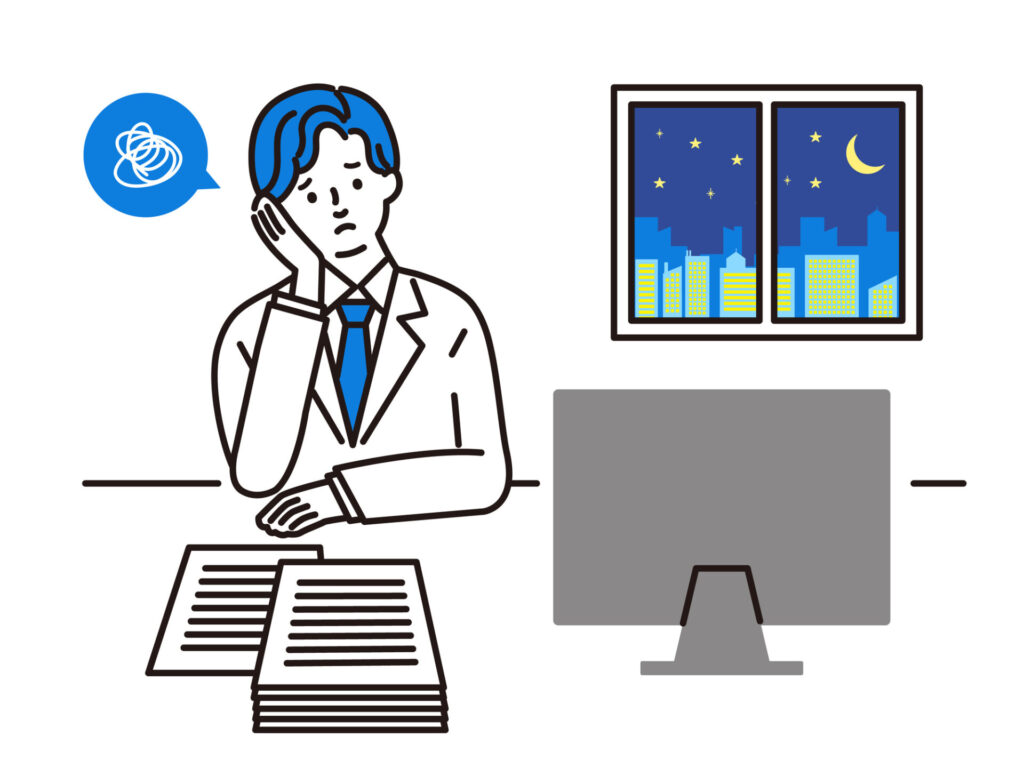
医師は長時間労働が常態化している仕事であり、2024年4月1日に働き方改革がスタートした後でも、残業時間が多い傾向にあります。「医師の残業時間をどうすれば削減できるのか」と頭を悩ませている経営者や労務管理担当者の方も多いのではないでしょうか。
医師の残業時間を削減するには長時間労働の現状を把握し、適切な対応で解決に導くことが大切です。
本記事では医師の残業時間を説明した上で、長時間労働の現状と具体的な解決策を紹介します。
医師の残業時間はどのくらいか?

残業(時間外労働)とは、労働基準法で定められている法定労働時間を超えおこなう労働のことです。
法定労働時間は1日8時間・1週間40時間であり、医師の場合も法定労働時間に違いはありません。つまり1日8時間・1週間40時間を超えた部分の労働時間が、残業時間に該当します。
※法定休日に出勤した場合は残業ではなく休日労働として扱います。
厚生労働省によると、2022年に実施した調査の結果、医師の1週あたりの労働時間は下記のとおりでした。
| 1週あたりの労働時間 | 回答者の割合 |
|---|---|
| 週40時間未満 | 22.5% |
| 週40時間以上50時間未満 | 32.7% |
| 週50時間以上60時間未満 | 23.7% |
| 週60時間以上70時間未満 | 12.1% |
| 週70時間以上80時間未満 | 5.4% |
| 週80時間以上90時間未満 | 2.3% |
| 週90時間以上100時間未満 | 0.9% |
| 週100時間以上 | 0.9% |
参考:厚生労働省ホームページ:「医師の勤務実態について」
法定労働時間内で働いている場合は1週あたりの労働時間が「週40時間未満」になるため、残業や休日労働が発生している医師は77.5%もいることが分かります。特に週40時間以上60時間未満は50%を超えていて、医師の約半分が週1時間~20時間未満の残業が発生している状況です。
なお、労働時間が週60時間を超えると時間外・休日労働時間は年換算960時間以上となり、該当する医師は21.2%となっています。さらに、週80時間を超えた場合の時間外・休日労働時間は年換算1,920時間以上で、該当する医師は3.7%です。
医師の働き方改革後は残業時間に上限規制がある

2022年の調査において医師に長時間の残業や休日労働が発生していた理由は、もともと医師の時間外労働に上限規制がなかったためです。どれだけ残業をしても法律上の問題がないことから、多くの医師が残業を余儀なくされていました。
しかし、2024年4月1日にスタートした医師の働き方改革により、医師の時間外労働に上限規制が設けられました。医療機関と医師が36協定を締結した場合に、医師の時間外労働は下記の区分で上限が設けられます。
| 医師・医療機関の区分 | 長時間労働の理由 | 年の時間外労働の上限 |
|---|---|---|
| A水準 | すべての勤務医を対象とした原則の上限規制 | 960時間 |
| 連携B水準 | 兼業医師の労働時間を他院と通算すると長時間労働になるため | 通算1,860時間 (各院で960時間) |
| B水準 | 地域医療の確保に必要であるため | 1,860時間 |
| C-1水準 | 臨床研修・専門研修の集中的な訓練を行うため | 1,860時間 |
| C-2水準 | 高度な技能の修得を行うため | 1,860時間 |
参考:厚生労働省ホームページ「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」
医師の働き方改革の実施後は、A水準の「年960時間」が原則的な医師の時間外労働の上限です。連携B水準~C-2水準に該当する場合でも「年1,860時間」が上限となり、1,860時間を超える医師の労働は法律上認められていません。
また、医師の働き方改革では長期的な計画として、すべての医療施設においてA水準を満たすことを目標としています。連携B水準・B水準は段階的に解消して2035年末に終了する予定であり、C-1水準・C-2水準も縮減予定です。
さらに、医師と36協定を締結せずに時間外労働をおこなわせた場合や、上限規制を超える労働を行わせた場合は労働基準法違反となり、使用者には罰則が科されます。罰則の内容は、いずれも6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金です。
E参考:-Gov法令検索「労働基準法」
医師の時間外労働の上限規制が明確に定められたことにより、医師を取り巻く労働環境は大きく変化しています。医師の労働時間が1,860時間を超えるケースはなくなり、全体的な残業時間は減少が期待できるでしょう。
医師の働き方改革後も長時間労働が発生する理由

医師の働き方改革によって、残業を含む医師の時間外労働に上限規制が設けられました。
しかし、時間外労働の上限規制だけで医師の長時間労働がなくなったわけではありません。上限規制の範囲内における長時間労働は依然として問題視されています。
以下では、医師の働き方改革後も長時間労働が発生する理由を4つのポイントに分けて解説します。
医師不足が深刻化していて残業を避けにくい
日本は医師不足が深刻化していて、地方で医師が確保しにくくなる「地域偏在」や、診療科によって医師数に大きな差がつく「診療科偏在」といった問題が発生しています。医師不足の医療機関では限られた医師数で医療を提供しなければならず、医師の残業を避けにくい状況です。
医師の働き方改革は医業に従事するすべての医師を対象としており、医師不足の医療機関であっても時間外労働の上限規制が適用されます。
しかし、医師不足の医療機関で残業をなくすことは容易ではないため、以前より残業時間は減るとしても、A水準(上限960時間)やB水準~C水準(上限1,860時間)の範囲内で残業時間が発生すると考えられます。
【参考記事】
医師偏在はなぜ起こる?問題点や対策について解説
医療業界の人手不足の原因とは?解決策についても解説
地方で医師不足にお困りの方へ。遠隔読影サービスがおすすめの理由を解説
医師の時間外労働の上限規制は比較的緩い
医師の長時間労働がなくならない理由の1つが、医師の時間外労働の上限規制が比較的緩いことです。
一般的な職業における時間外労働の上限は、「月45時間・年360時間」が原則となっています。特別条項付きの36協定を締結した場合でも、「年720時間・2~6か月平均80時間以内(休日労働含む)・月100時間未満(休日労働含む)」を超えることはできません。
対して、医師の時間外労働の上限は、36協定を締結した場合の原則であるA水準でも「年960時間」です。その他の規制も適用されず、代わりに追加的健康確保措置を講ずることが定められています。
医師の仕事には医療業務のほかに研修や当直、学会への参加などがあり、上限時間内での長時間労働が発生する可能性は高いといえます。
業務効率化が進んでおらず、医師に業務負担が集中している
小~中規模な医療機関において業務効率化が進んでいないことも、医師の長時間労働が発生する原因です。
医療現場ではさまざまな事務作業が発生し、医師が医療以外の業務に煩わされるケースは珍しくありません。厚生労働省が2016年におこなった調査によると、医師業務の中で負担に感じるものは下記の3つが突出して多くなっていました。
- 主治医意見書の記載
- 診断書、診療記録及び処方せんの記載
- 診察や検査等の予約オーダリングシステム入力や電子カルテ入力
参考:厚生労働省ホームページ「平成28年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成28年度調査)の報告案について」
主治医意見書や診断書、診療記録の記載などは、デジタル化を進めることで業務プロセスを簡略化できます。予約オーダリングシステム入力や電子カルテ入力も、医師以外のスタッフが担当できるようになれば医師の業務負担を軽減可能です。
総合病院や大学病院といった規模が大きい医療機関は設備投資をしやすく、デジタル化への対応を比較的進めやすいでしょう。 しかし、規模が小さい病院や診療所ではデジタル化を進めにくく、医師に業務負担が集中して残業が発生しやすい環境となっています。
>>病院の業務を効率化するにはどうすればいい?業務効率化のメリットや実現するためのポイントなど解説
患者さまやご家族の方からの理解が得られにくい
医師の長時間労働をなくすには、医療機関を受診する患者さまやご家族の方の協力が不可欠です。しかし、医業は一般的に公共性が高いサービスと考えられており、医師の労働時間について理解を示してくれる方は多くありません。
診療時間外に医療機関を利用しようとしたり、主治医による診療のみを要望したりする方もいます。いずれも医師の業務負担を増やし、残業時間の発生につながる行為です。
患者さまやご家族の方からの理解が得られないままでは、医師の長時間労働を減らすことはできません。医療機関は、患者さまやご家族の方にも医師の働き方改革の内容を周知し、協力を仰ぐ必要があります。
医師の残業時間を減らすための解決策5選

医師の残業時間を減らすには、医師を雇用する医療機関が主体的な取り組みを実施することが必要です。厚生労働省が提供している医師の働き方改革関連のページなどを参考に、医療機関がどのような取り組みを行えるかを調べるとよいでしょう。
最後に、医師の残業時間を減らすために医療機関が実施できる5つの解決策を紹介します。
医師労働時間短縮計画を作成する
まずは医師労働時間短縮計画を作成しましょう。
医師労働時間短縮計画とは、医師の労働時間を短縮するために医療機関内で取り組む事項などを明記した計画のことです。医療機関は計画に基づいてPDCAサイクルを回し、労働時間短縮の取り組みを進めます。
医師労働時間短縮計画に記載する内容は下記の2つに分けられます。
【共通記載事項】
- 労働時間数
- 労務管理、健康管理
- 意識改革、啓発
- 計画の作成プロセス
【任意記載事項】
- タスクシフト/シェア
- 医師業務の見直し
- 勤務環境改善やICTなどの設備投資
- 副業、兼業を行う医師の労働時間管理
- 臨床研修医や専攻医の研修効率化(C-1水準の適用時)
医師労働時間短縮計画は、連携B水準・B水準・C-1水準・C-2水準の指定申請をおこなうときにも必要な書類です。A水準を超える長時間労働が発生する医療機関は、忘れずに作成しましょう。
参考:厚生労働省ホームページ
医師の働き方改革
「医師の働き方改革」とは
医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(令和6年11月改正版)
労務管理ができるシステムを導入する
医師の長時間労働を防ぐには、労働時間を正確に把握することが重要です。労務管理ができるシステムを導入して、医師の労働時間や残業時間、休日労働時間を管理しましょう。
特に救急対応や訪問診療をおこなっている医療機関や、副業・兼業を行っている医師がいる場合は、システムによる労務管理の必要性が高まります。医師の労働時間を把握できていないと、時間外労働の上限を超える可能性があるためです。 出勤時間・退勤時間の自動打刻や、副業・兼業先の勤務時間の合算ができるシステムを導入すると、医師の労働時間を正確に把握できます。
タスクシフト/シェアを推進して医師の業務負担を軽減する
医師の残業時間を減らす直接的な取り組みが「タスクシフト/シェアの推進」です。
タスクシフト/シェアとは、医師が従来行っていた業務の一部または全部を他医療従事者に移管したり、業務の共同化をしたりすることです。タスクシフト/シェアを推進すると医師の業務負担が軽減されて、残業時間の削減を実現できます。
例として、下記のような業務について、現行制度の下でもタスクシフト/シェアが可能とされています。
- 看護師による特定行為(38行為21区分)の実施
特定行為研修を修了した看護師は、医師があらかじめ作成した手順書によって特定行為を行えます。
- 心臓・血管カテーテル検査と治療における臨床検査技師による検査装置の操作
心臓・血管カテーテル検査と治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作は、医師の指示の下で臨床検査技師が行えます。
- 診療放射線技師による放射線検査などの説明と同意書の受領
放射線検査の実施にあたって患者さまにおこなう放射線検査の説明と同意書の受領は、診療放射線技師が実施できます。
参考:一般社団法人 日本病院会ホームページ「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」
患者さまやご家族の方に働き方改革を周知する
医師の働き方改革を実施するには、患者さまやご家族の方の協力が必要です。自院を現在利用している方はもちろん、これから利用する方に対しても、医師の働き方改革の内容を周知しましょう。
具体的な取り組みとしては、「患者さまに診療時間内の受診をお願いする」ことが挙げられます。患者さまが診療時間内の受診を意識すれば、診療時間外の業務が少なくなって医師の残業時間を減らすことが可能です。
また、「主治医以外の医療従事者による対応」にも理解を求めましょう。患者さまが1人の主治医に依存しなくなることで、タスクシフト/シェアによる業務分散を成功させやすくなります。
外部の医療関連サービスに業務を委託する
医師に大きな業務負担がかかっている医療機関では、外部の医療関連サービスの利用も検討しましょう。外部の医療関連サービスに業務を委託することで、医師の業務負担が軽減できて残業時間の削減につながります。
たとえば、健診業務などで読影に多くの時間が必要となる場合、外部の医療関連サービスとして「遠隔画像診断サービス」を活用することが有用です。遠隔画像診断サービスでは、CTやMRIで撮影した医用画像の読影を、外部の企業や医療機関に委託できます。自院の読影医にかかる業務負担を軽減するとともに、検査精度の向上も期待できるサービスです。 外部の医療関連サービスは他にもさまざまな種類があります。長時間労働につながっている業務を把握した上で、解決につながるサービスを選ぶとよいでしょう。
遠隔読影・遠隔画像診断サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>遠隔読影とは?選ぶ上での注意点・料金など分かりやすく解説
まとめ

医師は長時間労働が発生しやすい仕事で、週1時間以上20時間未満の残業時間がある方が多い傾向です。医師の働き方改革によって時間外労働の上限規制が設けられたものの、上限内の長時間労働は今後も発生すると考えられます。
医師の長時間労働を解決するには、労務管理システムの導入やタスクシフト/シェアの推進などをおこないましょう。あわせて、外部の医療関連サービスを活用し、負担が大きい業務を外部事業者に委託することも一つの方法です。
読影業務に多くのリソースが必要な医療機関の方は、遠隔画像診断サービスのイリモトメディカルにご相談ください。イリモトメディカルでは30名以上の放射線診断専門医・各科専門医による読影と、AIの二重読影によって見落としを防止し、安定した読影精度を提供いたします。
【監修者】
煎本 雄一(いりもと ゆういち)
株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長
2013年より医療業界に携わり、健診施設や医療機関向けの遠隔画像診断サービスを提供。
2021年より株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長。
医師・医療オペレーター・営業担当者・総務スタッフ・エンジニアなど多くのスタッフと日々連携し、診療や健診の質的な向上と効率化の両立を目指し、多面的な支援に取り組んでいる。
![この記事の監修者、煎本 雄一(いりもと ゆういち)[株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長]の写真](https://irimotomedical.co.jp/wp/wp-content/themes/irimotomedical/assets/images/column/supervisor.jpg)

