Column コラム
2025.05.07
地域医療連携とは?課題と解決策について徹底解説

2025年に全人口の5人に1人が75歳以上の後期高齢者となる日本では、今後医療への需要がますます高まっていくと考えられます。しかし、医療費の増加や医療従事者の不足、地域による医療格差などさまざまな医療問題を抱えており、解決に向けて早急に取り組むことが求められています。
これらの医療問題を解決するにあたって、重要なポイントになるといわれているのが地域医療連携です。
本記事では、地域医療連携の目的や役割、強化することによるメリットを紹介するとともに、地域医療連携における課題や解決策についても詳しく解説していきます。
地域医療連携とは

地域医療連携とは、その地域の医療機関が役割や機能を分担し、医療を必要とする人が適切なサービスを受けられるようにする仕組みのことを指します。かかりつけ医や高度な医療設備・専門医を有する病院など、規模や機能の異なる医療機関が役割を分担して連携することにより、急性期から回復期、慢性期までの医療を居住する地域で継続的に受けることが可能になります。
この地域医療連携は、国の政策である「地域医療構想」を実現するための取り組みのひとつです。地域医療構想は、人口構造やその地域の医療ニーズの変化を見すえ、各医療機関の機能の分化や連携を促進し、質の高い適切な医療を効率的に提供する体制の確立を目的とするものです。
この構想では、医療を必要とする人が等しく医療サービスを受けられる体制をつくるために、かかりつけ医を担う地域の医療機関と、大学病院などその地域の中核となる病院の連携強化を求めています。
地域医療連携の目的と役割

地域医療連携の目的には、おもに以下の2点が挙げられます。
- 地域に対するスムーズな医療提供
- 医療リソース分配の適正化
ここでは、それぞれの目的について解説していきます。
地域に対するスムーズな医療提供
地域医療連携のもっとも大きな目的は、その地域で医療を求める人に対し、急性期から回復期・慢性期まで切地域医療連携のもっとも大きな目的は、その地域で医療を求める人に対し、急性期から回復期・慢性期まで切れ目なくスムーズに医療を提供することです。
それぞれの地域は、以下のように規模や役割が異なる医療機関を有しています。
- かかりつけ医の役割を担うクリニックや個人医院
- 診療密度の特に高い医療を提供する高度急性期病院
- 一般的な急性期の患者に医療を提供する急性期病院
- リハビリなどおこなう回復期病院
- 長期療養が必要な患者を受け入れる慢性期病院
- 在宅診療に対応するクリニックなど
これらの医療機関が互いに連携して役割や機能の分担を明確化することにより、適切で質の高い医療をスムーズに提供することが可能になります。また、地域医療連携には、福祉施設や介護施設・ソーシャルワーカーなど、他の職種と連携して包括的なケアをおこなうことも求められています。
医療リソース分配の適正化
医療リソースの分配を適切におこなうことにより、より効率的に質の高い医療サービスを提供することができます。
物的リソースとしては医療機器が挙げられます。医療技術の進歩により、診療や検査に使用する医療機器も精度が向上し、導入には高額な費用がかかるようになりました。しかし、高額な最新の医療機器を複数の医療機関で共同購入して共有をすれば、よりレベルの高い医療を地域に展開できるでしょう。
人的リソースでは医師の配置が課題のひとつです。たとえば、産婦人科の患者が多い病院にはより多くの産婦人科専門医を配置し、慢性疾患をもつ高齢者が多く通う病院には内科の専門医を重点的に配置するなど、医師を集約化することで地域の医療レベル向上に期待ができます。しかし、そのためには地域の医療ニーズを的確に把握することが需要です。
地域医療連携が必要とされる背景
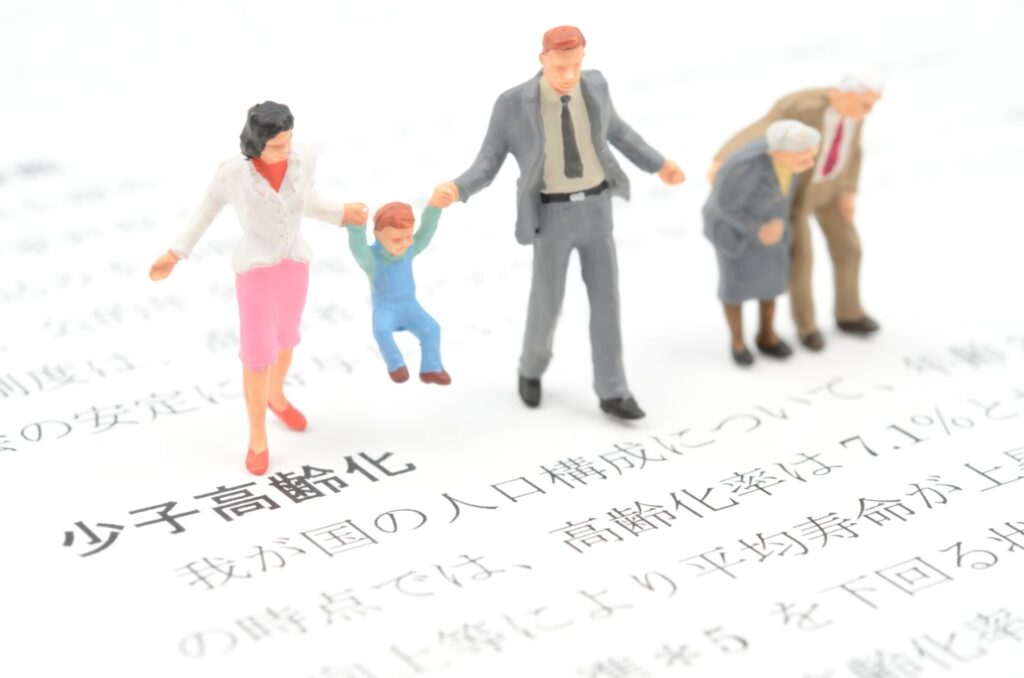
少子高齢化が進む日本においては、早急に地域医療連携を強化・推進していくことが求められています。この背景には、人口動態が大きく関わっています。
冒頭でも述べたように、2025年には団塊の世代全員が75歳を超え、日本人の5人に1人が75歳以上の後期高齢者となります。今後も高齢化は進展して2065年にピークを迎え、おおよそ3.9人に1人が後期高齢者になると推計されています。
高齢化が進むことで医療に対する需要が高まり、働き手である若年層への労働負担が大きくなっていくと考えられています。また、医療費の自己負担率が低い高齢者の増加するため、診療報酬削減など、国の社会保障費のさらなる増加も懸念されます。
また、このような状況は効率的な医療サービスの提供を阻み、治療を必要としている人に適切な医療を提供できず、命を奪う結果につながってしまう恐れがあります。これらの問題を避けるために、地域の医療連携体制の確立による適切な医療サービス提供を推進する動きがみられるようになりました。
地域での医療連携体制の構築を後押しするために策定されたのが「地域医療構想」です。
地域医療連携のメリット
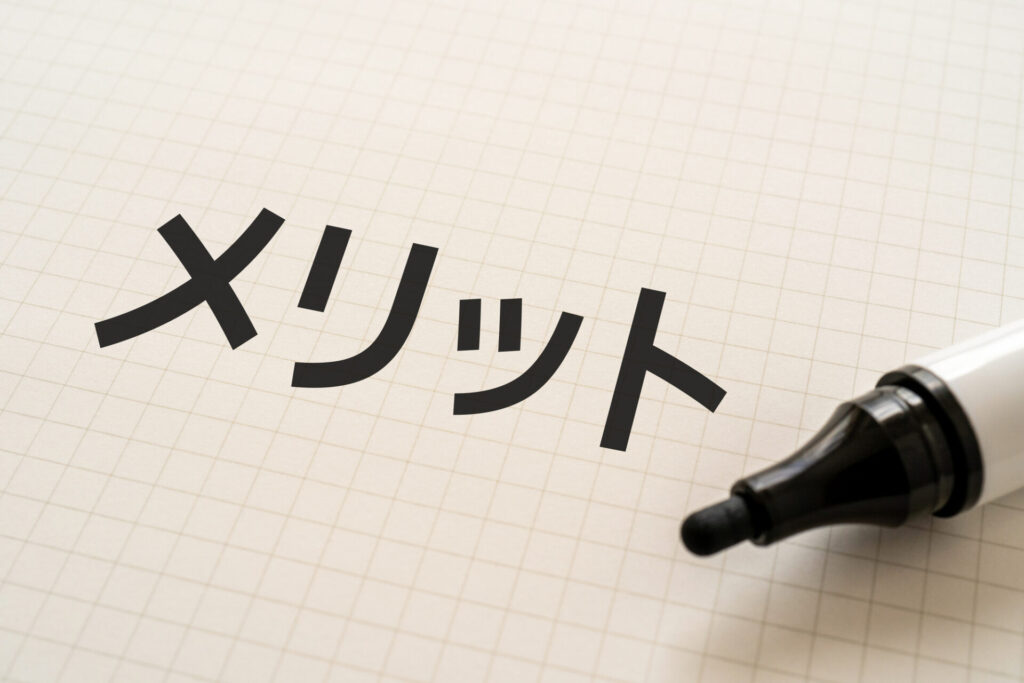
ここまで、なぜ地域医療連携の強化・推進が求められているのか、その背景や目的について説明してきました。では、地域医療連携によって具体的に医療現場にはどのような効果がもたらされるのでしょうか。
ここでは、地域医療連携のメリットについて解説していきます。
機能に応じた医療提供
地域医療連携で医師が適正に配置されることにより、それぞれの医療機関は得意とする診療分野に集中できるようになります。その結果、質が高くより専門的な医療サービスを提供することが可能になるでしょう。たとえば、脳卒中の患者に対しては、急性期は脳神経外科を有する病院、回復期はリハビリ専門病院など、状態に応じた医療機関を選択することで適切な治療をおこなうことができます。
また、医療リソースの分配が適正化することで、一部の医療機関への業務の偏りも解消され、その地域の医療リソースが無駄なく効率的に活用されるようになるでしょう。
スムーズな診療の実現
地域の医療連携体制が整うことで、かかりつけ医から紹介・逆紹介のシステムも機能するようになり、患者に対して適切な治療をスムーズに提供できるようになります。さらに、ICTの導入で医療機関のあいだで診療情報の共有が可能になれば、必要な情報も事前に入手でき、検査や投薬の重複を防ぐことができます。
また、オンライン診療の活用により、過疎地や離島など、医療リソースが限られている地域に対しても適切な医療サービスを届けることができると考えられます。
【参考記事】
地域医療の課題とは?問題点と具体的な解決策を解説
地方で医師不足にお困りの方へ。遠隔読影サービスがおすすめの理由を解説
医療従事者の負担軽減
地域医療連携によって患者が適切な医療機関を受診できるようになり、医師の診療範囲の適正化にも期待できます。医師は自らが専門とする分野の患者の診療に集中できるため、業務の負担も軽減され、質の高い医療を提供することが可能になります。
また、ICTの活用により、診療情報提供書をはじめとした書類作成や、検査・画像データ結果のコピー・発送業務についても効率化できるため、医師以外の医療従事者の業務も大幅に軽減ができます。さらに、電子カルテやオンライン診療・電子処方箋など、医療情報を共有する連携システムの構築を推進していくことにより、医師だけではなく、医療従事者全体の業務負担の軽減し、患者に対してスピーディーかつ適切な医療が提供できるようになると考えられます。
【参考記事】
医師の働き方改革における課題や問題点について解説
医療業界の人手不足の原因とは?解決策についても解説
医師の残業時間はどのくらい?長時間労働の現状と解決策について解説
地域医療連携における課題

地域医療連携は、厚生労働省主導のもとで各自治体が協議し、積極的に取り組んでいくことが求められています。しかし、地域医療連携を推進していくうえで、解決しなければならない課題があるのが現状です。
ここからは、地域医療連携における課題について説明していきます。
医療機関の機能役割が不明確
医療リソースの分配を適切におこない、地域医療連携の体制を構築していくためには、各医療機関の機能や現有する診療能力・役割を正しく把握しなければなりません。
しかし、それぞれの医療機関の現状は、外部からでは把握するのが難しいのが事実です。たとえば、医療設備や人員数に問題はなかったとしても、診療科によっては一人の医師が不在になっただけも患者の受け入れができなくなるなど、外部からはうかがい知れない問題を抱えている可能性がないとはいえません。
このように、医療機関の機能や果たせる役割が不明瞭であることは、地域医療連携の体制を構築していくうえで解決が必要とされる課題のひとつとして挙げられます。
医療リソースの地域偏在
過疎地などの人口が少ない地域では、医師や医療機関などの医療リソースそのものが不足していることがあります。
日本の医師数は増加の傾向にあるものの、都市部に集中しており、地方では依然として医師不足の状態にあります。同様に、そのほかの医療従事者や事務に携わるスタッフも、少子高齢化の影響による労働人口の減少により十分な人員を確保できない地域があります。
地域医療連携を強化していくためには、このような地域による格差をいかに平準化していくか検討し、しかるべき対策を講じる必要があります。
医療DX推進・ICT活用の遅れ
地域医療連携を円滑に進めるためには、各医療機関のあいだで診療情報を正確かつ迅速に共有することが求められます。
しかし、医療現場におけるDX推進はまだ十分であるとはいえず、電子カルテの普及率を例に挙げると、一般病院では57.2%、一般の診療所では49.9%という結果になっています。
医療機関によっては、システム導入や専門スタッフ採用の予算を確保できないこともDX化やICT活用推進を妨げる要因になっていると考えられます。また、すでに導入している情報システムが、ほかの医療機関のシステムと互換性がないというケースもあり、今後の対応が必要とされています。
【参考記事】
医療ICTとは?導入のメリット・デメリットや活用例について解説
地域医療連携における課題の解決策
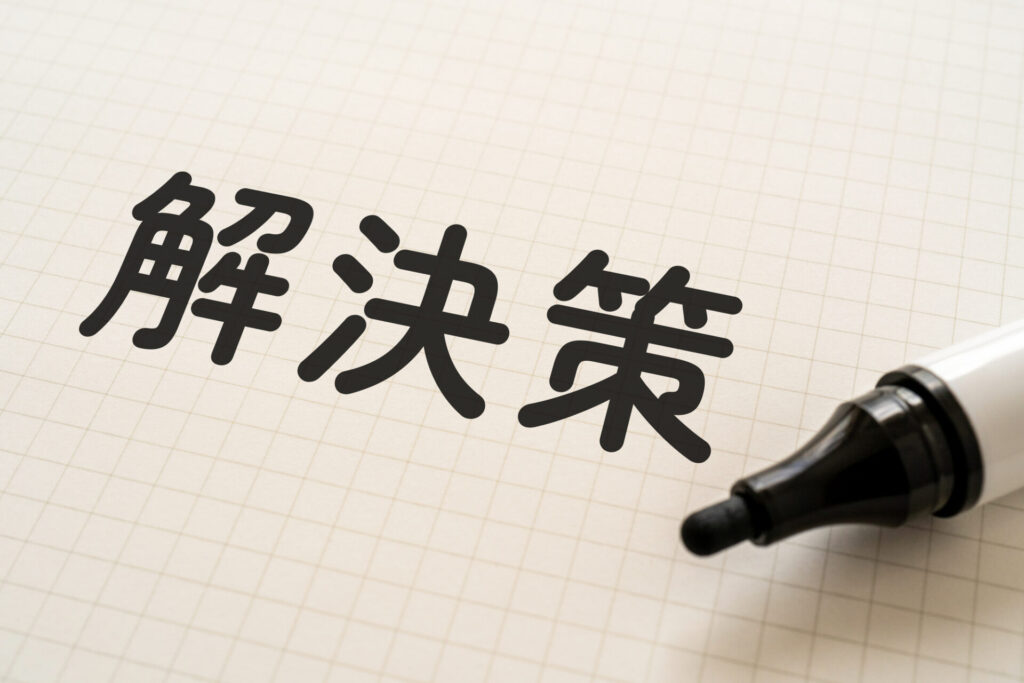
前項では、地域医療連携の課題について紹介してきました。
ここからは、これらの課題をどのように解決して地域医療連携を強化・推進していけばよいのか、解決策について解説していきます。
地域医療構想による医療機関の連携・役割分担
厚生労働省では、中長期の人口推計をもとに地域の医療ニーズと病床の必要数を推計し、全国に341の構想区域を設定して、以下の4つの医療機能ごとに本来必要とされる病床数を推計しています。
- 高度急性期病院
- 急性期病院
- 回復期病院
- 慢性期病院
この「地域医療構想」は、地域による病床数の偏りや現状を共有し、医療サービス提供体制の実現を目指すものです。全国341の構想区域それぞれに「地域医療構想調整会」を設置し、その地域の現状に応じた地域医療を実現するための協議が実施されています。
地域医療連携推進法人制度の施行
「地域医療連携推進法人制度」とは、質が高く適切な医療を提供するための指針を定め、地域医療連携を推進する一般社団法人を各都道府県知事が認定する制度です。
認定の基準としては、診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院のうちのいずれかを運営する2つ以上の法人が参画し、患者団体や医師会、そのほかの組織で構成される「地域医療連携推進評議会」を法人に設置していることが挙げられています。
地域医療連携進法人制度により、以下のような医療連携が実現するとされています。
- 地域内での医療人材の育成・教育
- 地域での医療資材・薬品などの共同購入
- 各法人共同で開催する研修・講習
- 地域内での医療サービス・介護に関する新たな試み
参考:厚生労働省ホームページ「地域医療連携法人制度について」
地域医療支援病院制度の導入
「地域医療支援病院」とは、地域の中核病院としてかかりつけ医を支援し、その地域全体の医療の質の向上を支援する病院を指します。各都道府県知事によって承認され、2023年9月の時点で700の地域医療支援病院が地域医療の中核を担っています。
地域医療支援病院の役割としては、開放型病床の運営、高額な医療機器の共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者への研修の4つが挙げられ、この制度により、地域医療連携がより強化されることに期待されています。
かかりつけ医制度(紹介・逆紹介)の推進
2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
この制度は、患者ははじめにかかりつけ医を受診し、必要に応じて地域の中核病院などの医療機関への紹介を受け、紹介された医療機関での治療終了後、再びかかりつけ医への逆紹介を受けてケアを継続するという一連の流れを推進するものです。
かかりつけ医制度の導入には、医療の機能分化推進のほかに、地域の包括ケアシステムで重要な役割を担う「かかりつけ医の機能を有する医療機関」を明確にするという目的があります。また、この制度では中核病院がかかりつけ医との医療連携体制を構築することを目指していますが、かかりつけ医への逆紹介を実施することで、患者の継続的なケアが実現するだけではなく、中核病院の業務負担の軽減にも寄与すると考えられています。
医療DX・ICT活用の促進
地域の医療機関が互いに連携していくうえで重要なポイントになるのが情報共有です。
地域医療連携を強化していくためには、積極的に医療DXやICTの活用を推進していく必要があります。
ICTを活⽤した情報共有のひとつとしては「医療情報連携ネットワーク」が挙げられます。患者の診療情報・処方薬の内容・検査結果など、必要な情報をネットワークを通じて閲覧することが可能ですが、情報を共有するにあたっては患者の同意を得ることが条件となります。
医療情報連携ネットワークの利用により、病院やクリニック・薬局・訪問看護ステーションなど、地域における多くの医療機関のあいだでスピーディーかつ効率的な情報共有が可能となり、患者に対して質の高い適切な医療サービスが提供できると考えられています。
ただし、医療情報連携ネットワークを利用するためには、カルテや検査データがデジタル化(DX化)されている必要があります。200床以下の病院の電子カルテの導入率はいまだ50%に届かず、さらなる普及が求められています。
まとめ

本記事では、地域医療連携が必要とされる背景や目的、推進するにあたっての課題や解決策について解説してきました。
少子高齢化が進むことで医療ニーズがますます高まっていく日本では、医療従事者の不足や地域による医療格差など、さまざまな医療問題の解決が求められています。これらの問題を解決する施策のひとつとして、地域医療連携が挙げられます。
地域医療連携を推進していくためには、地域の各医療機関の機能と役割を明確にし、医療リソースを適切に分配することが重要です。また、かかりつけ医制度の紹介・逆紹介を実施することで、患者の継続的なケアと中核病院の負担軽減を図り、高齢化社会の多様化した医療ニーズに対応していくことも課題だと考えられます。
また、地域で滞りなく医療連携をおこなうためには、スピーディーかつ正確に情報を共有しなければなりません。医療情報連携ネットワークの利用など、医療DX・ICTの活用に積極的に取り組むことで、質が高く適切な医療サービスの提供が可能になるでしょう。
イリモトメディカルでは、遠隔読影サービスの提供を通じて地域医療連携をサポートします。30名以上の放射線診断専門医・各診療領域の専門医が、画像検査の読影に幅広く対応し、スピーディーに読影結果を報告いたします。地域に放射線専門医が不足している、あるいは不在という医療機関の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【監修者】
煎本 雄一(いりもと ゆういち)
株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長
2013年より医療業界に携わり、健診施設や医療機関向けの遠隔画像診断サービスを提供。
2021年より株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長。
医師・医療オペレーター・営業担当者・総務スタッフ・エンジニアなど多くのスタッフと日々連携し、診療や健診の質的な向上と効率化の両立を目指し、多面的な支援に取り組んでいる。
![この記事の監修者、煎本 雄一(いりもと ゆういち)[株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長]の写真](https://irimotomedical.co.jp/wp/wp-content/themes/irimotomedical/assets/images/column/supervisor.jpg)

