Column コラム
2025.02.28
がん検診で見落としを防ぐには?原因や対策について解説

がん検診は、がんの早期発見を目的として検査をおこない、病態の悪化を未然に防ぐことで対象者の健康維持につなげています。しかし、実際のところがん検診によるがんの見落とし事例が複数報告されています。
がん検診の診断は医師の個人スキルも影響するものですが、見落としをできる限り減らすにはどのようにすれば良いのでしょうか?
この記事では、がん検診で見落としが起こる原因や対策について具体的に解説していきます。
がん検診に見落としはある?

がん検診の診断は100%正確ではなく、少なからず見落としのリスクが存在します。どんなに優れたがん検診でも完璧な精度は期待できず、対象者の個人差も影響します。
実際のところ、がん検診や健康診断・人間ドックなどでのがんの発見は、がん患者全体の15%程度であるのが現状です。がん検診は自覚症状のない人のがんを早い段階で発見し、早期治療につなげる重要な役割を果たしますが、がんの種類や場所によっては発見が難しい場合もあります。
厚生労働省の報告によると、がん検診の未受診の理由の一つとして「がん検診を受けても見落としがあると思っている」が挙げられています。日本でがん検診の見落とし事例が増えていくと、このような未受診のケースが増えることにより、結果的に治療が遅れ致命的な状態につながる対象者が増加する可能性も否定できません。
がん検診の見落としのリスクを極力減らすためには、その原因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。必要に応じて医療機関で適切な対策をとることで、国民の健康状態を維持することにもつながるでしょう。
参考:厚生労働省ホームページ「がん検診受診率向上に向けたこれまでの取組」
がん検診で見落としが発生する原因

がん検診で見落としが発生する主な原因は以下の4つです。
- 医療画像の読み誤り
- 読影医の不足
- 画像診断報告書の読み忘れ
- 医療従事者間の連絡ミス
がん検診で見落としが起きてしまう理由は医師の診断ミスだけではありません。詳しい原因を学んでいきましょう。
医療画像の読み誤り
がん検診の見落としで多いは、読影医の技術、画像の画質や撮影条件、がんの部位などの要因が影響します。
特に膵臓がんなどは観察が難しい場所に位置しているため、発見しづらい傾向にあるのが特徴です。また、人間ドックで採用されているPET検査などは、特定のがん種の発見に不向きな場合もあります。これらの要因により、医療画像の読み誤りが発生し、がんの見落としにつながる可能性があります。
読影医の不足
画像診断に対応する読影医の不足は、がんの見落としにつながる要因の一つです。日本では読影業務を中心に携わる放射線診療専門医の数が減少しているため、適切な対策を取っていない医療機関では、読影医が不足する状況に陥りやすくなります。
その結果、読影業務に十分な時間がかけられず、見落としのリスクが高まります。読影医の不足は、がん検診における診断の質の低下につながる可能性があり、早急な対策が必要です。
読影医不足の解決策については、以下の記事でも解説していますのでご覧ください。
>>読影医が不足している現状と解決策について解説
画像診断報告書の読み忘れ
画像診断報告書の読み忘れは、がん検診において見落としにつながる重大な原因です。読影医が作成した画像診断報告書に記載されている所見を、主治医が十分に確認しないことで、がん検診の見落としが発生するケースがあります。
画像診断報告書の読み忘れによって、実際にがんの治療が遅れたトラブルも報告されています。この問題の背景には、医療機関内で業務量の偏りがあり、医師が読影業務に十分な時間を割けないことなどがありました。医療スタッフ間の業務配分によっては、業務量を均等に分配することも必要になるでしょう。
医療従事者間の連絡ミス
医療従事者の間で連絡ミスが起こることで、誤ったがん検診の結果が受診者に伝わる可能性があります。同様に、入力データと検査結果を照合するための読み合わせを怠ったことによる検査結果の入力ミスが発生したケースも存在しています。
これらの人為的ミスは単純なものから重大なものまでさまざまですが、いずれもがんの見落としや誤診につながる可能性があるため甘く見てはいけません。このようなミスが続く場合は、医療機関内でのダブルチェック体制の強化や、情報共有システムの改善なども対策として必要となってくるでしょう。
がん検診で見落としを防ぐ方法

がん検診で見落としを防ぐ方法については、以下が挙げられます。
- 精度の高い検査機器を導入する
- 経験豊富な放射線診断専門医に読影を依頼する
- 遠隔読影サービスを導入する
がんの見落としを防いで精度の高い検査結果を提供するために、事前に学んでおきましょう。
精度の高い検査機器を導入する
医療機関に精度の高い検査機器を導入することで、がん検診の見落としリスクを軽減できる場合があります。画像解析の精度が高く、前がん病変の発見や、がんの早期発見につながる可能性が高くなるからです。
これらの検査機器は微細な異常も検出できるため、従来の検査機器で見逃されていた可能性のある病変を発見する確率が向上します。一方で、検出された微細な異常が偽陽性(※)や過剰診断(※)に極力つながらないように、がん病変を見極める読影スキルも必要です。
(※)偽陽性:がん検診でがんの疑いがあったにも関わらず、その後の精密検査でがんが検出されないこと。
(※)過剰診断:生命を脅かすリスクがない病変をがんと診断すること。がん検診や精密検査で発見されたがんが消えてしまったり、進行せず状態がとどまったりする。
経験豊富な放射線診断専門医に読影を依頼する
読影業務を専門とする放射線診断専門医に診断を依頼することで、より信頼性の高いがん検診の結果が得られる可能性が高まります。放射線診断専門医は豊富な経験と知識を持ち、微細な異常の見落としを生じさせない能力を持っています。さらに、画像診断の最新の診療技術や知見を常に学んでいるため、より正確に読影することが可能です。
すでに読影が済んでいる医療画像でも、放射線診断専門医によるダブルチェックを実施することで、がんの見落としのリスク軽減が期待できます。放射線診断専門医の診断は、早期がんの発見率を向上させ、患者の健康維持につながるでしょう。
【参考記事】
遠隔読影の比較基準とは?サービス内容・注意点など解説
遠隔読影サービスを導入する
医師不足によるがんの見落としが問題となっている医療機関では、遠隔読影サービスの導入が有効な解決策になり得ます。
遠隔読影サービスは、医療機関で撮影されたCT検査やMRI検査などの医療画像をインターネットを介して遠隔地の医療機関・企業に送信し、画像診断を依頼できるサービスです。遠隔読影サービスを利用することで、外部の放射線診断専門医・各診療科の専門医に読影業務を代行してもらうことが可能になります。
さらに、ダブルチェックなども実施できるため、がん検診における見落とし防止の有効な対策もなります。遠隔読影サービスは、放射線診断専門医や各診療科専門医の知見を広く活用できる点では、地方や過疎地、小規模の医療機関にとっても有益です。
遠隔読影サービスについては以下の記事でも詳しくご紹介しています。
>>遠隔読影とは?選ぶ上での注意点・料金など分かりやすく解説
がん検診の見落としで損害賠償責任が生じるケース

がん検診における見落としが全て医療機関の責任になるわけではありませんが、被害者が訴えた後、特定の条件がそろっていることが判明した場合に医療機関側に損害賠償責任が生じる可能性があります。特定の条件に当てはまるのは「損害」「過失」「損害と過失の因果関係」の3要素です。
【医療機関側に損害賠償責任が生じる可能性のある3つの条件】
- 損害:がん検診の見落としによって受診者の死亡、後遺症、精神的損害などが起きている
- 過失:がん検診の見落としは医療従事者の処置・対応(※)に落ち度がある
- 損害と過失に因果関係がある
(※)実際に医療画像を読み誤った場合だけでなく、主治医が画像診断報告書を読まなかったり、医療従事者間の連絡ミスが生じたりすることも含まれる。
しかし、医療画像から診断できる情報量にも限界があるため、医療画像の読み誤りが過失に該当するかどうかは慎重に検討する必要があります。医療機関側の責任を問うためには「医師が通常の注意義務を果たしていれば発見できたはずの異常を見落としたこと」が証明されなければなりません。これには、がんの種類や進行速度、見落としの期間なども考慮されます。
実際の判例では、肺がんで異常陰影を認識したものの、前年度と変化がないとして精査を勧めなかった事例で約5,400万円、大腸がんを糞塊と誤診した事例で約7,100万円の損害賠償が命じられたケースがあります。
がん検診の見落としに関するよくある質問
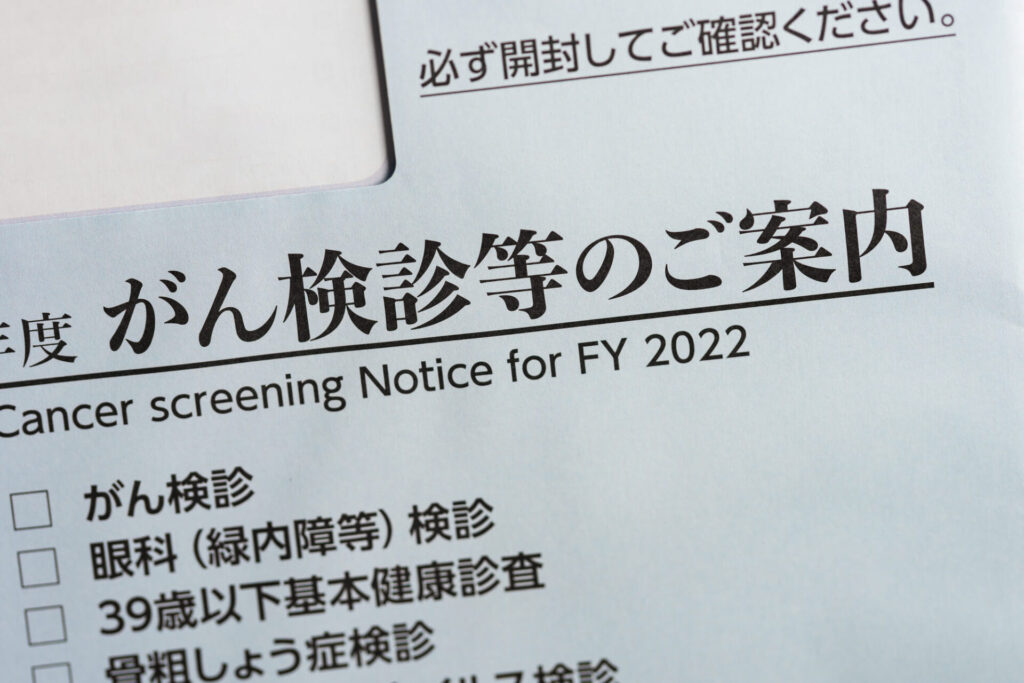
がん検診におけるがんの見落としでよくある質問についてまとめました。
- がん検診は「受けないほうがいい」といわれているのはなぜですか?
- 子宮頸がんの検診でも見落としはありますか?
- 健康診断や人間ドックのがん検査の見落としでも損害賠償責任は発生しますか?
それぞれについてお答えしていきます。
Q.がん検診は「受けないほうがいい」といわれているのはなぜですか?
がん検診を「受けないほうがいい」といわれる理由にはいくつかの要因が考えられます。
そのうちの一つは、がん検診には偽陰性(がんの見落とし)や過剰診断のリスクが存在することです。偽陽性の場合、不必要な不安や追加検査による身体的・精神的負担が生じる可能性があります。また、過剰診断では、生命に影響を与えない可能性のある病変に対して、不要な治療が実施されるおそれもあるのです。
もう一つの要因として、一部のがん検診で体に負担がかかる偶発症のリスク(内視鏡検査による鼻出血など)が生じることも挙げられます。
これらの要因が「受けないほうがいい」という考えにつながっている可能性があります。
Q.子宮頸がんの検診でも見落としはありますか?
子宮頸がんの検診でも見落としが発生する可能性はあります。
子宮頸がんの検診は、子宮頸部から採取した細胞の標本によって診断されますが、細胞の採取にミスが生じたり、診断の際に読み誤りが起きたりすると、がん検診の見落としにつながる可能性があります。子宮頸がんの見落としを減らすためにはこれらのミスを減らすように努力するだけでなく、受診者側に推奨されている頻度でがん検診を受けもらうことも重要です。
Q.健康診断や人間ドックのがん検査の見落としでも損害賠償責任は発生しますか?
健康診断や人間ドックのがん検査の見落としも、医療機関側の損害賠償につながる可能性があります。特に多いのは、医療画像を読み誤って損害が生じたケースです。
集団検診の場合は、複数の画像を短時間で読影する必要があるため、通常の診療とは異なる医療水準が適用される場合があります。しかし、集団検診だからといって直ちに過失が否定されるわけではなく、個別の状況に応じて慎重に判断されることが一般的です。
まとめ

がん検診の見落としは医療画像の読み誤りだけでなく、読影医の不足による多忙な業務形態や、画像診断報告書の読み忘れ、医療従事者間の連絡ミスなどでも起こります。がんの見落としを防ぐためには、精度の高い検査機器を導入したり、経験豊富な放射線診断専門医に読影・ダブルチェックを依頼したりすることが大切です。
また、がんの見落としによって被害者から訴えられた場合、損害と過失の因果関係が証明されれば、医療機関側に損害賠償責任が生じる可能性があります。場合によっては数百万〜数千万円の慰謝料を支払うケースがあることも頭に入れておきましょう。
がん検診の見落としが心配な場合は、読影を外部の病院や企業に依頼できる「遠隔読影サービス」を導入することも解決策の一つです。イリモトメディカルの遠隔読影では、30名以上の放射線診断専門医や各科の専門医が読影に対応いたします。また、薬事承認済みの高精度AIを活用しながらがん検診の見落としを徹底的に予防し、安定した読影が可能です。
遠隔読影サービスの利用を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
【監修者】
煎本 雄一(いりもと ゆういち)
株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長
2013年より医療業界に携わり、健診施設や医療機関向けの遠隔画像診断サービスを提供。
2021年より株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長。
医師・医療オペレーター・営業担当者・総務スタッフ・エンジニアなど多くのスタッフと日々連携し、診療や健診の質的な向上と効率化の両立を目指し、多面的な支援に取り組んでいる。
![この記事の監修者、煎本 雄一(いりもと ゆういち)[株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長]の写真](https://irimotomedical.co.jp/wp/wp-content/themes/irimotomedical/assets/images/column/supervisor.jpg)

