Column コラム
2025.08.28
遠隔読影とは?選ぶ上での注意点・料金など分かりやすく解説

医療業界において注目が広まりつつある遠隔読影。近年では、遠隔読影サービスを導入する医療機関が増えてきています。
しかし、遠隔読影とは一体何なのか、どのようなメリットがあるのかを、まだご存知ない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遠隔読影について詳しく解説した後、始め方やサービスを選ぶときの注意点、料金の相場などについてお話しします。
遠隔読影サービスの導入を検討している方は、ぜひ記事の内容を参考にしてみてください。
遠隔読影とは
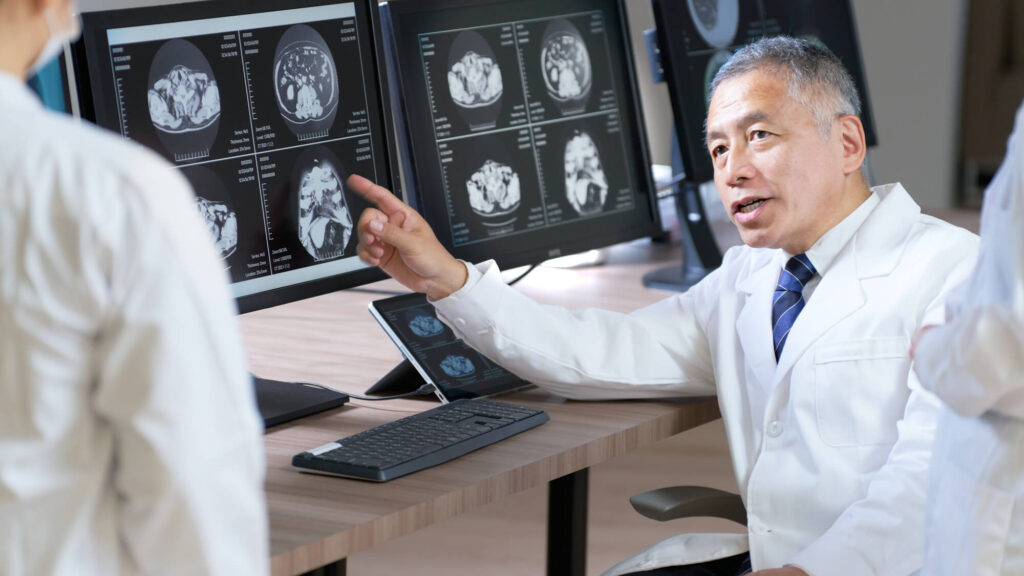
遠隔読影(えんかくどくえい)とは、病院やクリニックで撮影した患者の画像を、読影医師のいる企業や病院へネットワークを介して送信することで、画像診断レポートを受け取れるサービスのことです。遠隔読影を利用すると、専門医師が足りていない地域やクリニックなどの小規模な医療機関でも、精度の高い画像診断が可能になります。
遠隔読影では企業や病院の放射線や各診療科の専門医師にCTやMRI、マンモグラフィ、X線などの画像を送信し、読影を依頼します。その後、読影医師が画像を読影し、診断結果や所見、推奨される治療方法などが記載されたレポートを作成して、依頼元の医療機関に返送する仕組みです。
遠隔読影によって、地域間の医療格差の解消や診断の迅速化、医療の質向上などが期待できます。また、緊急時の対応や、まれに見られる疾患の診断にも利用できる点もメリットです。
また、遠隔読影と似たような用語に「遠隔画像診断」がありますが、一般的にはどちらも同じ意味として使用されることを知っておきましょう。
遠隔読影と院内読影の違い
遠隔読影と院内読影の主な違いは、読影を担当する放射線診断専門医が院内に常駐しているかどうかという点にあります。
院内読影では、医療機関内にいる専門医が、CTやMRIなどの画像をその場で確認し、診断を行います。一方、遠隔読影では、撮影した画像データを外部の専門医に送信し、遠隔地にいる医師が診断結果を提供する形式です。
院内に十分な数の専門医が確保できている場合には、遠隔読影を導入する必要はないかもしれません。しかし、医師の人手不足や人件費の制約といった事情により、常勤の専門医を配置するのが難しい医療機関にとっては、遠隔読影は非常に有効な選択肢となります。
遠隔読影サービスを導入するメリット

医療機関で遠隔読影サービスを利用すると、以下のメリットが期待できます。
- 読影医師不足の解消
- 専門医師によるレベルの高い読影
- 診療時間の短縮
それぞれ詳しく見ていきましょう。
読影医師不足の解消
遠隔読影サービスは、読影医師が不足している医療機関にとって、読影を代行してもらえる点が大きな魅力です。検査数と読影医師の人数が見合わない場合、遠隔読影を依頼することで、読影の質を維持しながら効率的に診療をすすめられるでしょう。
医師やそのほかの医療スタッフの負担が軽減されるため、緊急性の高い症例の対応などにも集中できるようになります。
専門医師によるレベルの高い読影
遠隔読影サービスには、放射線や各診療科の医師に専門性の高い読影を依頼できるメリットもあります。高度な専門知識を持つ医師が読影することが多いため、より信頼性の高い診断が得られることもあるでしょう。
専門医師が在籍していない場合でも、診断の質を安定させる手助けとなることが期待できます。
診療時間の短縮
医療機関における診療業務の圧迫を減らせることも、遠隔読影サービスのメリットといえます。
遠隔読影サービスでは読影のほかにも、詳細な情報が記載された読影レポートの作成まで読影医師に依頼できます。依頼元の医療機関は画像の分析や追加の検査の検討、治療の選択などに費やす時間が削減できるため、その分の時間をほかの診療に充てられるでしょう。
>>医師の残業時間はどのくらい?長時間労働の現状と解決策について解説
>>病院の業務を効率化するにはどうすればいい?業務効率化のメリットや実現するためのポイントなど解説
遠隔読影の画像診断管理加算について

遠隔読影を導入する場合、画像診断管理加算がつかないケースがあります。画像診断管理加算は、放射線診断専門医や読影に携わる医師が画像診断をする医療機関に対して認められる診療報酬の加算のことです。
画像診断管理加算は、企業やNPO法人の画像診断センターが提供している遠隔読影サービスを利用する場合は加算がつきません。しかし、遠隔画像診断施設基準の申請が厚生局に届け出されている病院間で遠隔読影をおこない、定められた条件に当てはまっている場合は、加算の対象となります。
遠隔読影の流れ

遠隔読影を依頼する際には、普段の診療どおりに画像を撮影した後、依頼先に画像を送信します。その後、依頼先で読影した結果などが記入されたレポートを受け取ります。
一連の流れについて詳しく見ていきましょう。
医療機関で画像を撮影
遠隔読影は、病院やクリニックなどの医療機関における画像撮影から始まります。通常の画像診断装置の設定と撮影技術により、問題なく読影できる品質の画像を撮影しましょう。必要に応じて複数の角度や断面の撮影をした後、画像と患者情報との紐づけもおこないます。
遠隔読影の依頼先へ画像を送信
画像の撮影が完了した後は、依頼先に画像データを送信します。画像データと共に読影依頼も送信します。読影依頼には患者の主訴や検査目的などを記載します。データを送信する際には、遠隔読影サービスが提供している管理システムを利用する場合が多いでしょう。
管理システムには、オンプレミス型(専用の機材や回線の導入が必要)とクラウド型(必要なのはインターネット環境のみ)があります。依頼先の企業を選ぶ際には、この点についても事前に確認のうえ、自身の医療機関に合ったサービスを選びましょう。
読影レポートを受け取る
遠隔読影の依頼先では、画像の読影をした後、診断結果や推奨する治療方針などが記載されたレポートを作成します。作成されたレポートは暗号化され、依頼元の医療機関にネットワークを通じて返送されます。
画像読影を依頼してからレポートが返送されるまでの時間は企業や病院によってさまざまです。レポートを受け取ったら、その内容をもとに患者の説明や治療計画の立案などをおこないます。
遠隔読影サービスの始め方

医療機関で企業による遠隔読影サービスを始めるときは、導入するサービスを選択した後、ネットワークなどの下準備やスタッフへの研修もおこなう必要があります。必要な準備や流れについて詳しく説明します。
遠隔読影サービスの選択
遠隔読影サービスを導入する際には、始めにさまざまなサービスを比較して選ぶ必要があります。遠隔読影サービスは多くの企業が提供しており、料金設定やセキュリティ対策、サポート体制など、特徴や強みが異なります。
ホームページで気になるサービスの企業に数件問い合わせて、提案を依頼すると良いでしょう。
必要なネットワークの準備
遠隔読影サービスを利用するには、高速インターネットの接続や医療用画像管理システム(PACS)などの導入が必要です。これらの準備は依頼先からサポートを受けられるケースが多く、インターネットの形式などによって必要な時間が異なります。サービスを連携する端末の数などによっては料金も大きく異なるため、見積もり時に確認しておきましょう。
サービスの利用開始
ネットワークとシステムの準備が整った後は、医療スタッフへ内容の伝達が必要です。システムの操作や一連の流れ、データ保護の重要性、緊急時の対応などについて研修を用いて説明します。スタッフ全体の教育を通して、患者ケアの向上と医療機関の運営の効率化を目指します。
遠隔読影サービスを選ぶ上での注意点

遠隔読影サービスをさまざまな企業から選ぶときは、以下の内容を事前に確認しましょう。
- 読影医の数と専門医資格の有無
- 緊急対応の有無
- 依頼したい検査内容に対応しているか
- 見落とし防止・記載ミス防止の対策をしているか
- レポート返送までの期間はどのくらいか
【関連記事】
遠隔読影の比較基準とは?サービス内容・注意点など解説
読影医の数と専門医資格の有無
遠隔読影サービスを選ぶときは、放射線の専門医師だけでなく、各診療科で依頼したい専門医師がいるかどうかも確かめましょう。遠隔読影サービスによって、従事している医師の診療科は異なります。読影医師の数が少ない場合は、レポートが返送されるまでの時間が長い可能性もあるため、返送までの時間も併せて確認できると良いでしょう。
緊急対応の有無
緊急時にすぐ対応してもらえるのかという点も、遠隔読影サービスを比較するときに確認すべきでしょう。たとえばネットワークが突然正常に接続できなくなった場合など、迅速な対応が必要となることも考えられます。総合病院や大学病院などの24時間稼働している医療機関では、夜間の体制についても確認しましょう。
依頼したい検査内容に対応しているか
遠隔読影サービスを導入するときは、CTやMRI、マンモグラフィ、胃部、胸部、眼底、単純X線画像など、読影を依頼したい検査内容に対応しているか必ず確認しましょう。サービスによって、検査内容の種類や得意分野も大きく異なります。将来的に使用する可能性がある検査内容まで含まれているか確かめるのがおすすめです。
>>眼底読影とは?選ぶ上での注意点・料金など分かりやすく解説
見落とし防止・記載ミス防止の対策をしているか
見落としを防止するための対策がとられているかについても確認するようおすすめします。
具体的には、ダブル読影やAIを活用した精査などにより、診断の精度が安定するような方法が採用されていれば安心できるでしょう。
レポート返送までの期間はどのくらいか
レポートが返送されるまでの期間も、遠隔読影サービスを選ぶときの重要なポイントです。読影を依頼後、レポート返送までは2~3営業日ほどかかることが多いですが、オプション料金を支払うことで、1時間以内に返送してもらえるケースもあります。依頼先によって異なりますが、確認しておくことをおすすめします。
遠隔読影サービスのセキュリティ

遠隔読影サービスでは、CTやMRIといった医療画像や患者情報を、インターネットを通じて他の医療機関や専門企業とやり取りする必要があるため、情報漏洩(ろうえい)を防ぐための高度なセキュリティ対策が不可欠です。
現在、多くの企業が遠隔読影サービスを提供しており、その中にはセキュリティ体制の強化に特に注力している事業者も存在します。しかし、安全な運用を実現するためには、サービス提供側だけでなく、利用する医療機関側もセキュリティへの意識を持ち、適切な対応をおこなうことが求められます。遠隔読影を安全かつ円滑に活用するには、双方が連携してセキュリティ体制を整え、個人情報や診断データの保護に努めることが重要なのです。
セキュリティの高い遠隔読影サービスの特徴
セキュリティ対策が整っている遠隔読影サービスの特徴は、以下の通りです。
遠隔読影サービスを検討される際の、参考になさってください。
紙媒体や記憶媒体が厳重に管理されている
遠隔読影サービスを選ぶ際は、ネット上のデータ通信だけでなく、紙資料や記録媒体(DVD-ROMなど)の取り扱いも含めて、適切な管理体制が整っている企業を選ぶことが大切です。たとえば、印刷されたレポートや記録メディアを施錠保管し、不要となった媒体を専門業者により適切に廃棄処理しているような企業であれば、より高いレベルでのセキュリティが期待できます。
災害時のトラブルにも対応している
セキュリティ体制を強化したい場合は、災害やトラブルといった予期せぬ事態にも対応できる支援体制の有無にも注目しましょう。全国にサポートセンターを設けていたり、24時間対応のオペレーションセンターを備えていたりする企業であれば、緊急時のフォロー体制にも安心感があります。さらに、データセンターの拠点を複数に分散して運用している企業であれば、自然災害などによる情報の消失リスクも低減できます。
プライバシーマークやISMS認証を取得している
プライバシーマークやISMS認証の取得企業は、個人情報の管理体制において一定の基準をクリアしているため、セキュリティ面でより信頼できるといえます。
プライバシーマークは、個人情報の適切な取り扱いを第三者機関が認めた証であり、消費者や取引先からの安心感にもつながります。
一方、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証は、国際規格に準拠した情報セキュリティ管理体制が構築・運用されていることを示すもので、企業としての信頼性や安全性の高さを客観的に証明する役割を担っています。
遠隔読影のセキュリティ対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>遠隔読影・遠隔画像診断のセキュリティは安全なのか?分かりやすく解説
遠隔読影サービスの料金

企業の遠隔読影サービスに必要な料金には、導入時の初期費用、基本料金としての月額費用、依頼ごとの読影費用などがあります。それぞれの内訳や相場について見ていきましょう。
初期費用・月額費用
遠隔読影サービスの初期費用と月額費用の相場は以下になります。
- 初期費用:5万~20万
- 月額費用:3万~8万
※初期費用は、サービスを連携する端末台数により大きく変動することもあります。
初期費用がどの範囲まで含まれているかはサービスによってさまざまです。上記の相場は、インターネットの形態や専用回線の設置費用、サポート費用などが含まれた金額になります。
院内の複数のパソコンで医療用画像管理システムやレポートを見られるように連携したり、電子カルテシステムから直接読影依頼ができる仕組みを導入したりすると、50万~300万円ほど追加になる可能性もあるのです。
月額費用は院内でサービスを設定するパソコンの台数によって異なるケースもあります。スライス加算や部位加算がサービスとして設定されていない場合は、その分金額が高額になる可能性もあります。
読影費用
遠隔読影にかかる費用には、読影費用とスライス加算、部位加算等があり、相場は以下になります。
- 読影費用:1件500〜3,500円
- スライス加算:一定のスライス数(100枚や200枚など)を超えると枚数分の料金が追加
- 部位加算:1部位1,000〜3,000円
スライス加算はCT/MRI検査画像で一定スライス数以上の画像が含まれる検査の読影で適用される追加料金です。読影のなかには診断の精度を保つために、より多くのスライス数が必要になるケースもあります。スライス加算の基準となるスライス数は企業によって異なり、一定のスライス数以上を超えるとスライス数分の料金が加算されます。
部位加算は複数の部位を撮影した検査画像の読影で追加される費用です。必要な部位を効率的に読影したり、診断の精度を高めたりする目的があります。複数の部位を撮影して読影依頼するときは、それぞれの部位に対して加算がつく可能性もあるのです。
スライス加算と部位加算は、サービスによって加算されない場合もあります。その他、夜間や休日の依頼時において時間外対応料金が必要になることもあるため、事前に確認しておきましょう。
遠隔読影サービスの費用を抑える方法

企業の遠隔読影サービスの導入費用を抑える方法としては、以下が考えられます。
無駄な費用を支払わないためにも、ぜひご確認くださいませ。
不必要なサービスを省く
遠隔読影サービスの費用をできるだけ抑えたい場合は、不要なオプションが含まれていないサービスを選ぶことが重要です。遠隔読影サービスには企業ごとにさまざまなオプションが用意されており、たとえば夜間診療を行っていないクリニックであれば、24時間対応の緊急サポートを外すことで、毎月の費用を抑えることができるでしょう。
システムをクラウド型にする
システムの提供形式によっても初期費用に差が出ます。オンプレミス型ではなくクラウド型を選択することで、専用機材や通信回線の導入が不要になり、導入コストを抑えられることはもちろん、サービス利用までの期間も短縮できます。なお、どちらを提供しているかは、企業によって異なるため、確認が必要です。
数社から見積もりを受ける
複数の企業から見積もりを取ることも大切です。特に初期費用については、企業ごとに大きな差があるため、希望する条件を明確にしたうえで比較することで、適正な費用感を見極めやすくなります。ただし、価格だけに注目すると、サービス品質の違いを見落とす可能性もあるため、コストと内容のバランスを総合的に判断することが求められます。
遠隔読影の費用について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>遠隔読影の費用相場とは?価格や注意点など分かりやすく解説
遠隔読影に関するよくある質問

最後に、遠隔読影に関するよくある質問に回答いたします。
遠隔読影サービスのご利用を検討されている方は、参考になさってください。
Q. 遠隔読影の精度は高いの?
遠隔読影が適切に実施された場合、通常の読影業務と同等かそれ以上の高い精度を実現できると考えられています。すでにお伝えいたしましたが、遠隔読影は豊富な経験と高度な専門資格を持った放射線専門医や各診療科の専門家が担当します。専門分野に特化した読影医が担当することで、特定の疾患や症状に関するより深い洞察が得られる場合もあるため、一般的な読影では見逃されやすい微細な変化や、まれな症例も適切に診断される可能性が高まるのです。
遠隔読影の制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>遠隔読影の精度は高いのか?専門医の視点から徹底解説
Q. 二重読影とはなんですか?
二重読影とは、X線検査や内視鏡検査などで作成された検査画像を読み解く読影を、2人以上の医師が別々に行う方法です。読影医にもミスは起こる可能性があり、結果として見落としが発生することもあります。この見落としを防ぐために、読影を二人以上で行って診断の精度を高めることが二重読影の目的です。
なお、特定のがん検診では二重読影が必須とされています。
二重読影について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>二重読影とは何か?その意義と行うべき理由を解説
Q. 遠方でも適切な診断はできるのですか?
はい、遠方でも適切な遠隔読影診断は可能です。
インターネットを通じて高精度な画像データの送受信が可能となっており、地理的な距離に関係なく、専門の放射線診断医による正確な読影が受けられます。
また、通信環境やセキュリティ体制が整ったサービスを利用すれば、患者様の大切な医療情報を安全に取り扱うことができ、都市部と同等レベルの診断品質が確保されます。医師不足や専門医が在籍していない地域においても、遠隔読影は有効な選択肢となっています。
>>地域医療の課題とは?問題点と具体的な解決策を解説
>>地方で医師不足にお困りの方へ。遠隔読影サービスがおすすめの理由を解説
まとめ

遠隔読影とは、ネットワークを介して撮影した画像を読影医師のいる専門施設へ送信することで、画像診断とレポート作成を外部に委託できるサービスです。読影医師が不足していても、専門医師による読影により診断の質を安定させられたり、診療時間が圧迫されなくなったりするメリットがあります。
さまざまな企業が提供している遠隔読影サービスを選ぶときは、従事している専門医師の数や、緊急トラブル対応と依頼したい検査内容の有無などを確認した上で比較検討しましょう。
また、利用開始にあたり、どのような管理システムや専用端末の導入が必要となるかはサービスによって異なります。諸設定についてはサポートを受けられる場合もありますが、準備の負担やスタッフが使いこなせるのかなども考えて比較すると良いでしょう。
遠隔読影サービスにかかる料金は主に読影費用と初期費用、月額費用です。特に初期費用の相場は企業によって幅が広く、数百万円になるケースもあります。
イリモトメディカルの遠隔読影では、30名以上の放射線診断専門医や各科の専門医が読影に対応いたします。また、薬事承認済みの高精度AIを使用しながらがん検診の見落としを徹底的に予防し、安定した読影が可能です。
遠隔読影を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
【監修者】
煎本 雄一(いりもと ゆういち)
株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長
2013年より医療業界に携わり、健診施設や医療機関向けの遠隔画像診断サービスを提供。
2021年より株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長。
医師・医療オペレーター・営業担当者・総務スタッフ・エンジニアなど多くのスタッフと日々連携し、診療や健診の質的な向上と効率化の両立を目指し、多面的な支援に取り組んでいる。
![この記事の監修者、煎本 雄一(いりもと ゆういち)[株式会社イリモトメディカル 代表取締役社長]の写真](https://irimotomedical.co.jp/wp/wp-content/themes/irimotomedical/assets/images/column/supervisor.jpg)

